ソーダ水の泡は瓶より零れ出で泉をなしぬ夏のグラスに
“YouTubeなどのソーシャルメディアで有名な「tomei/透明愛好家」という人がいる。その名の通り、やや狂気を帯びて見えるほどに透明なものを愛好し、透明なケーキを透明なお皿で食べ、ガラスのティーポットで透明なお茶を沸かして飲み……という日々の暮らしを発信している人なのだが、夏になると彼女の透明な暮らしが無性に恋しくなる。生命あふれる季節だからこそ、無機質で澄んだものに触れたくなるのだろうか。
透明なものは少しおそろしく、そしていとおしい。スタロバンスキーの美しいルソー論『透明と障害』を思い出してもよいだろう。
「透明」というともう一つ想起されるのは、岡本かの子の傑作『鮨』。
その子供には、実際、食事が苦痛だった。体内へ、色、香、味のある塊団(かたまり)を入れると、何か身が穢れるような気がした。空気のような喰べものは無いかと思う。腹が減ると饑えは充分感じるのだが、うっかり喰べる気はしなかった。床の間の冷たく透き通った水晶の置きものに、舌を当てたり、頬をつけたりした。饑えぬいて、頭の中が澄み切ったまま、だんだん、気が遠くなって行く。(岡本かの子『鮨』)
「水晶の置きもの」は「天使の食べもの」だ。天使の食べものを食べることのできない人間の悲しさを思いながら、ソーダ水を少し口に含んでみる。”
作者/菅原百合絵(すがわらゆりえ)

1990年、東京生まれ。「心の花」会員。歌集に『たましひの薄衣』(書肆侃侃房)。本業はフランス文学研究。専門は十八世紀フランス文学・思想、とくにジャン゠ジャック・ルソー。
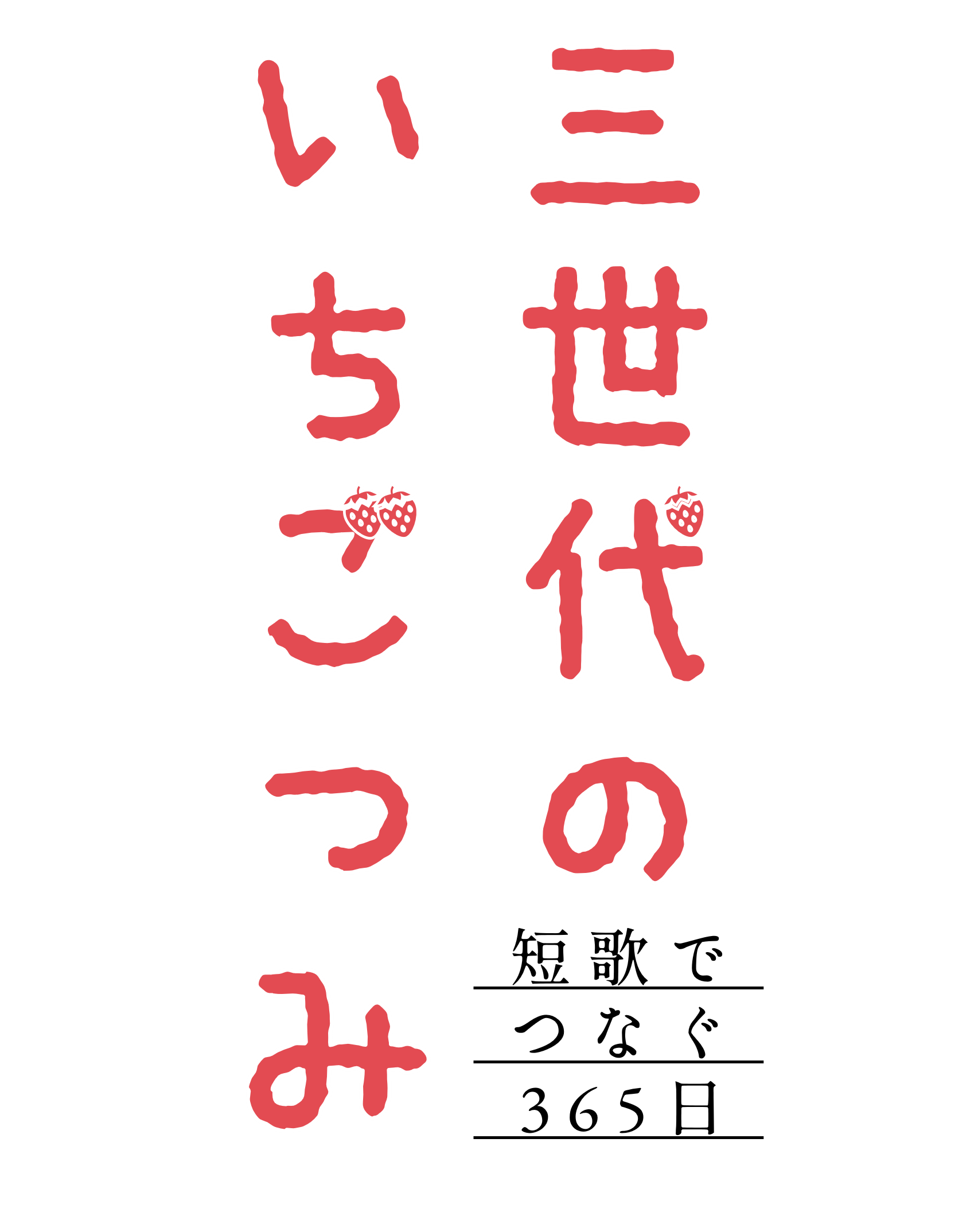

コメント